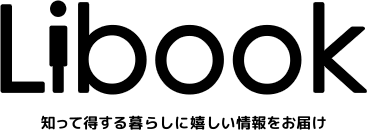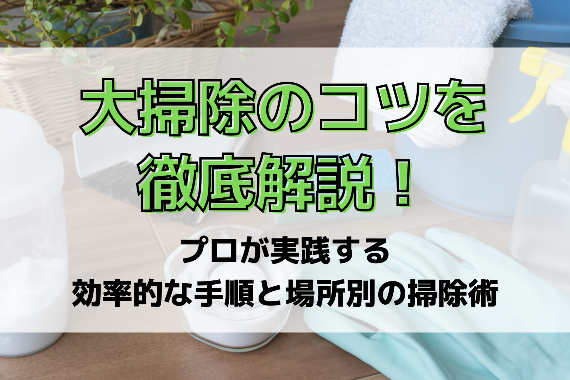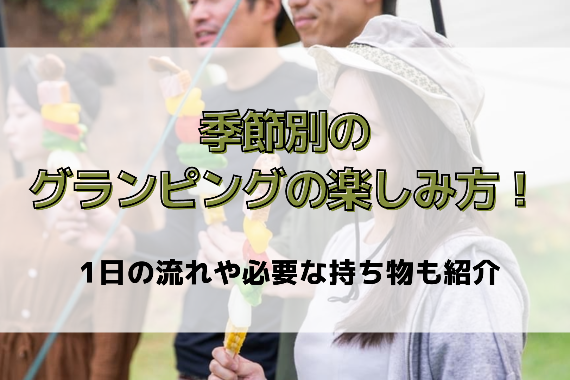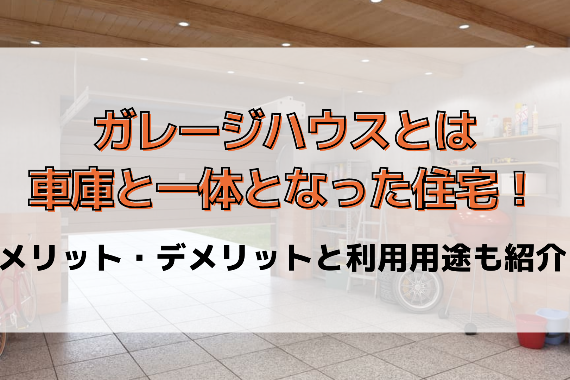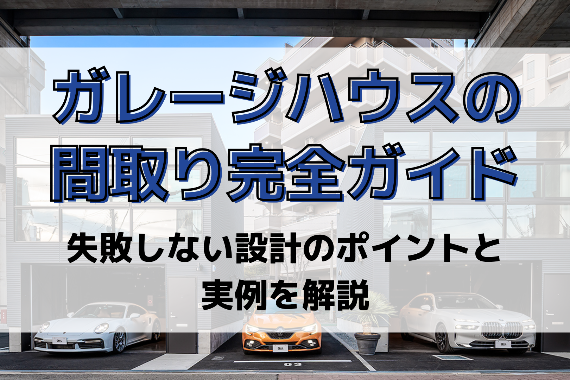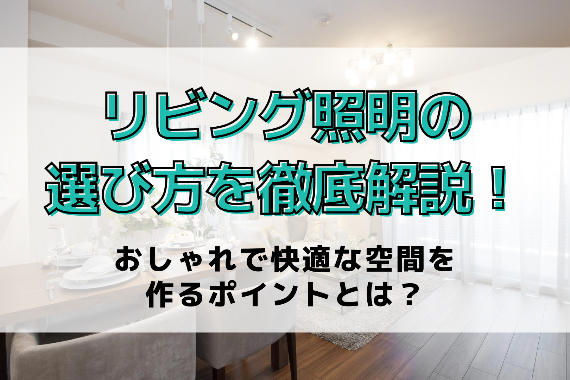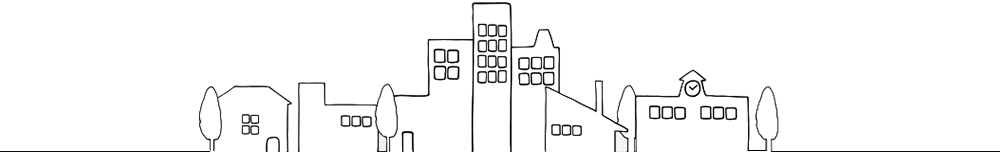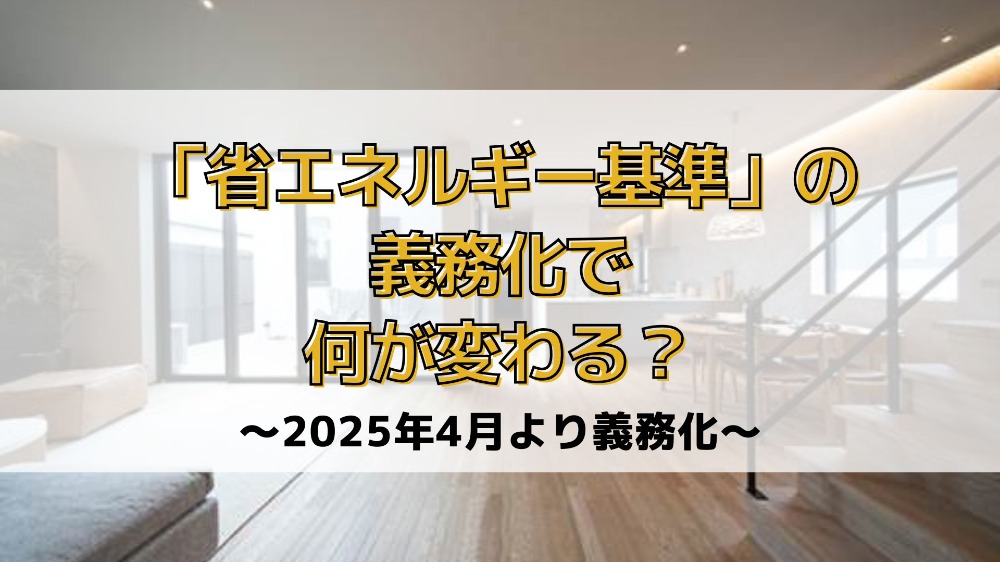
省エネルギー基準」の義務化で何が変わる?
~2025 年4 月より「省エネルギー基準の適合」が義務化~

2025 年4 月より「省エネルギー基準の適合」が義務化
2025 年4 月に「改正建築物省エネ法」が施行され、「省エネルギー基準」への適合が義務化されます。現在の制度では、一部の建物のみの適合でしたが、改正法の施行後は幅広い建物について省エネルギー基準への適合が義務付けられます。
―省エネルギー基準とは
省エネルギー基準とは、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」で定められた基準で、省エネルギー性能確保のために、建築物が備えるべき構造や設備に関する要件が定められています。「省エネルギー基準」は国のエネルギー政策の1 つで、省エネルギー技術の導入を促進するという目的があり、省エネルギー基準適合義務の内容は、2025 年4 月からは、原則としてすべての新築住宅や非住宅に対し、省エネルギー基準への適合が義務化されます。改正法が施行されれば、省エネルギー基準適合義務の範囲が大幅に拡大され、義務化の対象となる建築物については、建築確認手続きの際に「省エネルギー基準」への適合性審査が実施され、基準を満たさないと着工できなくなります。
―「建築物省エネ法」改正の背景
改正される背景には、目に見えるような現象を伴って地球温暖化が進み、これに伴う気候変動や世界的なエネルギー危機への対応として、世界中でカーボンニュートラルや脱炭素への取り組みが進められていますが、日本でも目に見える温室効果ガス排出削減への取り組みを推進する必要があるからです。―義務化の効果
建築分野がエネルギー消費量全体の約3 割、木材需要全体のうち約4 割を占めており、特に、エネルギー効率を向上させる積極的な取り組みが求められる分野です。「省エネルギー基準」の義務化で建物の断熱性能の向上やZEH(ゼロ・エネルギー・ハウス)の推進で再生可能エネルギーの利用が進み、エネルギー効率の向上が期待できます。こうした背景を踏まえて、2025 年4 月から幅広い建築物について省エネルギー基準への適合が義務化されることになりました。
関連記事:ZEH(ゼッチ)住宅とは? メリット・デメリットや補助金制度について詳しく説明!|Libook|近鉄不動産株式会社
「社会資産」としての住宅建築の時代
「省エネルギー基準の適合」義務化が始まり、住宅性能が平準化するということはどういうことなのでしょうか?今までも「省エネルギー基準」が無かったわけではありませんが、我が国では義務化されていませんでした。―これまでの住宅
ビルダーの多くは改正以前の最高等級(現行等級)「省エネルギー基準」等級4で住宅を建ててきました。多くビルダーは、省エネルギー基準を満足する住宅は建設していませんでした。国も様々な支援策を設けて省エネルギー化を推進してきましたが、欧米の住宅からは、はるかに性能や住宅寿命の短さで差を広げられてきました。―日本の住宅の評価
日本の住宅を国がどのように評価しているのか、その具体的な例を「固定資産税」の評価からくみ取ることができます。国によって評価が定められる「固定資産税額」は、客観的な資産価値の指標となります。関連記事:固定資産税とは土地や建物の所有者への財産税 計算方法や書類の見方を解説|Libook|近鉄不動産株式会社
―「固定資産税額」とは
「固定資産税額」は「土地と建物」それぞれの「固定資産税評価額」から算出され、建物の「資産評価」となる建物の「固定資産税評価額」は、床面積や建物の構造、付帯設備などから自治体によって決定されますが、簡単に言えば、建築にかかった費用が高い住宅ほど評価額は高めになります。「固定資産税評価額」は、一定ではなく原則的に築年数の経過と共に「減価償却」に応じて下がっていきます。―「減価償却」「耐用年数」とは
「減価償却」とは、長期にわたり使用される高額な資産の課税額を算出される際に使用される方法です。資産価値は購入時から年々下がっていくもので、持ち家の「構造により異なる耐用年数」が定められています。「資産価値」を定める基となる住宅についての「耐用年数」は現在、以下のように評価されています。○軽量鉄骨住宅(鉄骨の厚さ3mm以下)・・・19年(鉄骨の厚さ3mm以上~4mm以下)・・・27年
○重量鉄骨(鉄骨の厚さ4mmをこえるもの)・・・34年
○木造住宅・・・22年
○鉄筋コンクリート造住宅・・47年
「耐用年数」を超えた建物には、「資産価値」が無いと判断されることが多く、一般的には、「一戸建て(木造)は22年で価値が無くなる」といわれるのは、この耐用年数の短さのためです。耐用年数で定められた戦後の我が国の住宅は、実際にこの「耐用年数」に準じた住宅が多く、国の評価もこの程度のものだったのです。
耐用年数とは、あくまでも税金の算出に使用されるもので「耐用年数」が短いからといって、住宅に住めなくなったり、住まいとしての価値が完全になくなったりする訳ではありません。経年による最終残存率(下限)が20%に定められているため「耐用年数」を超えても「家屋の評価額」および「固定資産税」がゼロにもなりません。
―「社会資産」としての住宅とは
「社会資産」としての住宅とは、「耐用年数」が過ぎ「固定資産税」の評価が低くなってから、本格的な評価が定まる住宅です。国の木造住宅に対する評価は、このように低いものですが、木造住宅が持っているポテンシャルは、このようなものでないことは周知の通りです。江戸時代や明治期に建てられた住宅も、100 年住宅として現在も立派に機能している住宅がたくさんあります。―「木造住宅」も100 年住宅時代に
これから始まる「省エネルギー基準」の義務化は、日本の住宅、特に「木造住宅」が100 年住宅時代を生み出す基礎となる、基準にしなくてはなりません。それを可能にする技術力が日本の住宅メーカーには十分あります。この「木造住宅100 年時代」の目標を掲げて「省エネルギー基準義務化」という新時代に乗り出していきます。「地球温暖化対策」で国連の全加盟国が承認した「SDGs」。未来永劫に「地球環境と人類を守る」という約束は、人類共通の課題になり、「子や孫」のために「綺麗な地球環境」を残すことは、私達人類の努めでもあります。これから建てる住宅は、そのような決意を持って建てなければいけないと思っています。
当社では、2024年度以降に設計する全ての分譲戸建住宅について、ZEH基準の水準の省エネルギー性能を標準化しています。
当社分譲住宅についてはこちら