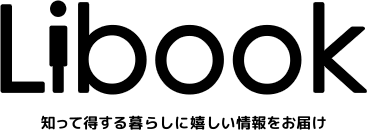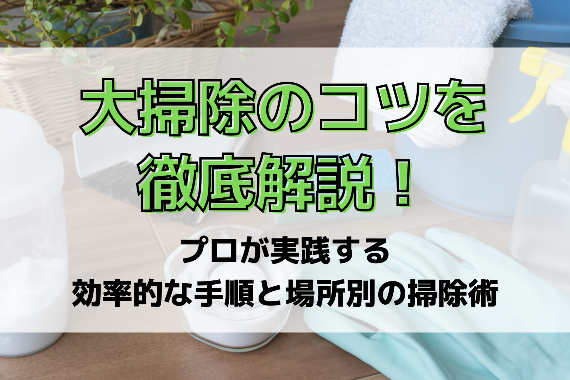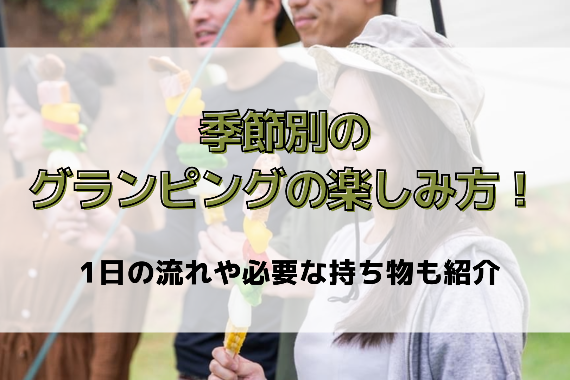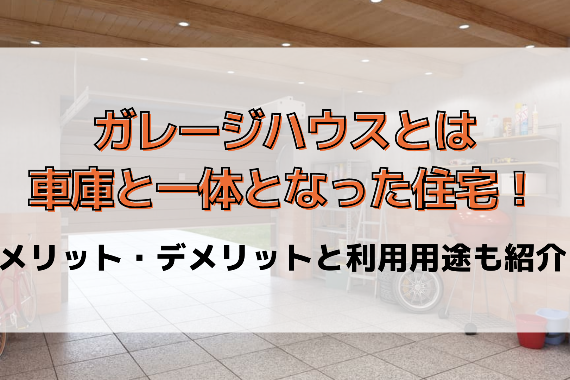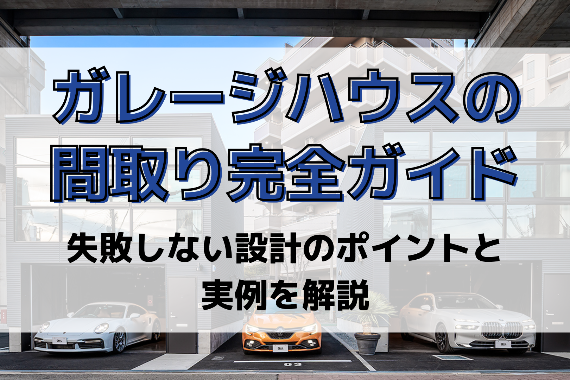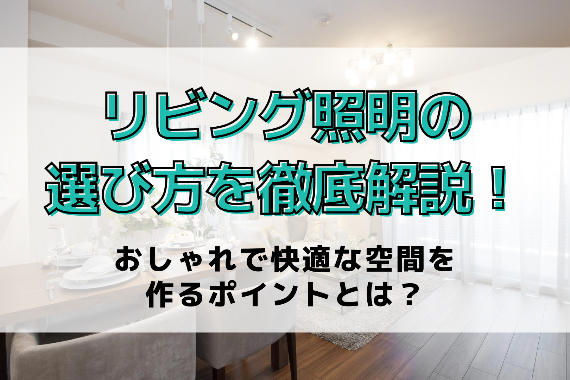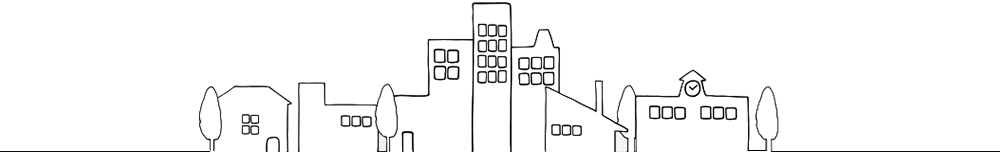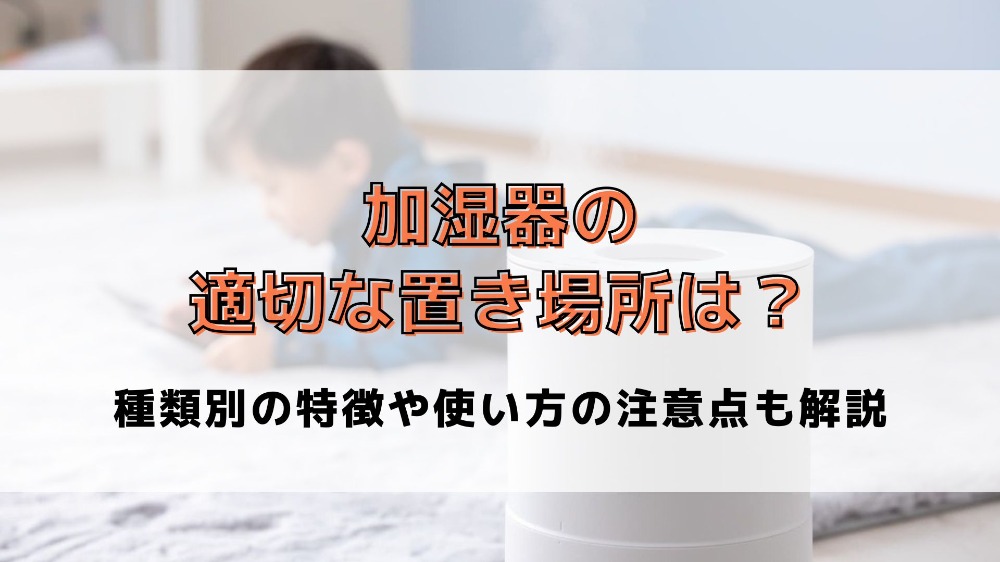
加湿器の適切な置き場所は? 種類別の特徴や使い方の注意点も解説

室内が乾燥しやすい冬場、多くの家庭で活躍するのが加湿器です。加湿器はエアコンなどで乾燥した室内の湿度を上げてくれる便利なアイテムです。
しかしせっかく加湿器を買ったけど、どこに置けばいいのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。加湿器は置く場所によって効果が大きく変わってしまう上、間違った置き方はカビや結露の原因にもなります。
そこでこの記事では、加湿器の効果的な置き場所や使用時の注意点などを詳しく解説します。加湿器を置く最適な場所が見つからないとお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
加湿器の適切な2つの置き場所

加湿器は、水蒸気を出して空気の湿度を上げる仕組みです。こちらでは最も効率的に部屋の中を加湿できる、おすすめの設置場所を2つ紹介します。
1.部屋の中央
部屋の中央は、最も効果的な加湿器の置き場所です。部屋の中央は放出された水蒸気が均等に四方へ広がりやすくなるため、最も効率的に部屋を加湿できます。特に広い部屋では、部屋の中央に設置するメリットは大きいでしょう。また部屋の中央に置くことで、壁や家具などに水蒸気が当たることを避けられます。水蒸気が壁や家具に当たると、カビが発生する原因にもなるため注意が必要です。レイアウトなどにも寄りますが、できるかぎり部屋の中央に設置することをおすすめします。
少し高い台の上
加湿器を設置する際の高さも、効果を左右する大切な要素です。床に直接置くよりも、ある程度の高さを確保することで、湿気が部屋全体に行きわたりやすくなります。温かい空気は上昇する性質があるため、ある程度の高さから水蒸気を放出することで、自然な空気の流れを作り出せるでしょう。理想的な設置場所としては、棚やテーブルの上が挙げられます。30cm〜1m程度の高さがあれば、効率的に水蒸気を拡散でき加湿器の効果をより実感できます。
避けるべき加湿器の5つの置き場所

加湿器の置き場所によっては、非効率になるばかりかカビの原因にもなります。こちらでは、避けるべき加湿器の置き場所を5つ解説します。
1.窓の近く
窓の近くは空気が冷えやすい場所です。窓の近くに加湿器を設置すると、放出された水蒸気がすぐに結露してしまう可能性が高くなります。結露は床や壁が濡れるだけでなく、カビの発生原因となり、家の劣化にもつながりかねません。特に冬場は窓ガラスの表面温度が室温より低くなるため、結露が起こりやすい状態になります。そのため加湿器は、窓から少なくとも1m以上離して設置することをおすすめします。
2.壁や家具の近く
壁や家具の近くも、加湿器の設置場所としては不適切です。加湿器から出た水蒸気が壁や家具に直接当たり続けると、その部分に湿気が集中して、カビ発生の原因となります。また木製家具は湿気に弱く、反りや歪みの原因になることもあります。壁紙が剥がれたり、壁内部に湿気が染み込んだりする可能性もあるでしょう。壁や家具を湿気から守るには、加湿器を50cm以上は離して設置することが必要です。
3.家電や紙類の近く
加湿器から放出される水蒸気は、電子機器や紙類にとって大敵です。水に弱い家電製品の近くに置くと、故障の原因となる可能性があります。特にパソコンやテレビなど、電子機器の近くに置くことは避けましょう。また本や書類などの紙類も、湿気によって傷みやすくなります。カビや変形の原因となるだけでなく、インクのにじみなども発生する可能性があります。
4.部屋の入口や換気扇の下
部屋の入口付近や換気扇の下は、空気の出入りが激しい場所です。空気の出入りの激しい場所に加湿器を設置すると、せっかく放出された水蒸気がすぐに外に流れ出てしまいます。加湿器の効率を高めるためには、部屋の入口付近や換気扇の近くは避けましょう。
5.エアコンの温風が直接当たる場所
多くの加湿器には、室内の温度や湿度を検知して自動で湿度を制御する機能が搭載されています。エアコンの温風が加湿器のセンサーに直接当たると、実際の室温よりも高い温度として検知されてしまい、適切な加湿制御ができなくなります。加湿器を正常に作動させるという点から、エアコンの温風が直接あたる場所は避けましょう。
4種類の加湿器の特徴を解説

加湿器は置き場所だけでなく、種類によっても特徴や注意点が異なります。以下に主な4種類の加湿器について解説します。
1.超音波式
超音波式は、超音波で水に細かい振動を与えて、霧状の微粒子を放出するタイプです。超音波式の最大の特徴は、消費電力の少なさです。消費電力が20W程度と省エネであるため、1ヶ月にかかる電気代が150~200円程度で済みます。また静音性が高いため、加湿器の動作音が気になるという方におすすめです。しかし超音波式は水を加熱しないため、タンクが汚れていると雑菌を一緒に放出してしまう点に注意が必要です。タンクの水は毎日交換し、定期的に清掃することが必要です。
また気化式やスチーム式に比べて放出する水の粒が大きいため、床や壁が濡れやすくなる点にも注意が必要となります。そのため壁や家具からは離れた場所に設置することが、他のタイプと比べて特に大切です。
2.気化式
気化式は、水を含ませたフィルターに風を送って自然に気化させるタイプです。超音波式と同様に消費電力が20W程度と少ないことが大きなメリットです。またファンがあるため、広範囲を加湿でき広い部屋での利用に適しています。ただし、加湿器から出る水蒸気は室温よりも低いため、室温が下がってしまうことがデメリットです。また急速な加湿にも不向きです。お手入れの面では、タンクの水を毎日取り換える必要があり、フィルターは週1回程度すすぎ洗いが必要です。フィルターの汚れがひどくなった場合には、交換も必要となります。
3.スチーム式(加熱式)
スチーム式は、水をヒーターで加熱して水蒸気を放出する方式です。水を沸騰させるため、超音波式や気化式のように雑菌が繁殖する心配が少なくなります。。また急速な加湿が可能で、寒い季節は温かい蒸気で室温を上げる効果もあります。デメリットは消費電力が大きいことです。スチーム式の消費電力は250~300Wで、1か月に約2,000円の電気代がかかります。また吹き出し口付近は高温になるため、小さな子どもやペットがいる家庭では注意が必要です。
4.ハイブリッド式
ハイブリッド式は「超音波式とスチーム式」と「気化式と温風気化式」の2つのタイプがあります。「超音波式とスチーム式」のハイブリッドは、ヒーターで加熱した水を超音波で霧状の微粒子にして放出します。スチーム式の衛生面でのメリットと、超音波式の静音性を合わせもっていることが特徴です。ただし、広い範囲の加湿ができないことに注意が必要です。
「気化式と温風式」のハイブリッドは、ヒーターで加熱された風を、水を含んだフィルターに当てて加湿します。ファンがあるため広範囲を急速に加湿でき、吹き出し口が熱くならないことが大きなメリットです。
ハイブリッド型は組み合わせによってそれぞれの利点を兼ね備えていることがメリットですが、本体価格は他のタイプに比べて高額です。
加湿器を使用する際の3つの注意点

加湿器を使用する際には、置き場所や加湿器の種類以外にも考慮しておくべき点があります。こちらでは加湿器の使用上の注意点を3つ紹介します。
1.就寝時には加湿器を止める
就寝中に暖房を止める場合は、加湿器を使用しないようにしましょう。室内の温度が下がっていくと、空気が含むことのできる水分量(飽和水蒸気量)も下がっていきます。その状態で加湿器がつけっぱなしになっていると、過剰な水分が結露となってカビが繁殖する原因となります。就寝時にも一定時間加湿器を利用したい場合は、タイマー機能が付いている製品を利用しましょう。
2.水蒸気を肌に当てない
加湿器は室内の湿度を調整するものであり、直接肌を保湿するものではありません。むしろ水蒸気を直接肌に当てると、水蒸気が肌の表面で蒸発する際に肌の水分も一緒に持っていってしまうため、乾燥の原因になる可能性があります。加湿器を肌の保湿のために利用することは逆効果になるため避けましょう。
3.ミネラルウォーターやアロマオイルを入れない
一般的な加湿器では、水道水以外の使用は推奨されません。ミネラルウォーターに含まれるミネラル分は、加湿器内部に付着して故障の原因となる可能性があります。またアロマオイルについても、専用の加湿器以外では使用を避けるべきです。オイルが内部の部品を傷めたり、プラスチック部分を劣化させたりする可能性があります。使用したい場合は、アロマオイル対応加湿器を使いましょう。
また浄水器の水の使用も避けるべきです。浄水器の水は水道水とは異なり塩素が含まれていないため、内部で雑菌が繁殖しやすくなります。
加湿器は適切な置き場所を選ぶことで、高い効果を得られる

加湿器は、適切な場所に設置することで最大限の効果を発揮します。「部屋の中央」や「適度な高さのある場所」が効果的です。一方で窓際や壁・家具の近くは過度な湿気によりカビの発生原因になるため避けましょう。また、水分に弱い電化製品や本や書類の近くに置くことも避けるべきです。
加湿器は種類によって特徴や注意点が異なるため、使用環境や目的に合わせて適切な種類を選択することが大切です。さらに就寝時の使用や水蒸気の当て方、使用する水の種類にも注意しましょう。
加湿器は適切な場所に置き、正しい使い方をすることで、快適な湿度環境を維持できます。この記事で紹介した内容を参考に、ぜひ自身にとって最適な加湿器の使用方法を見つけてください。