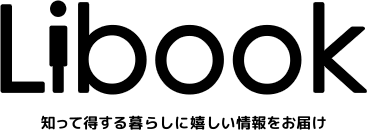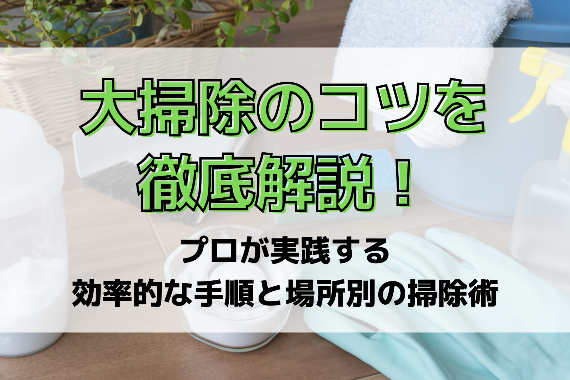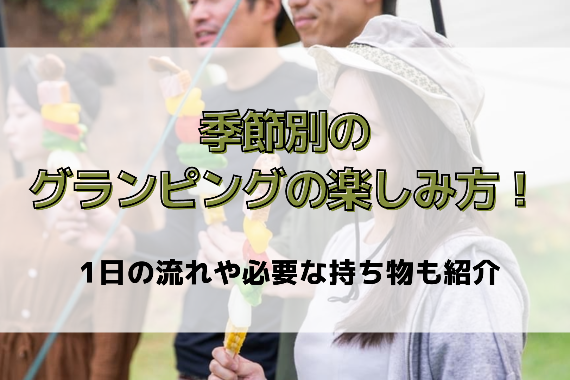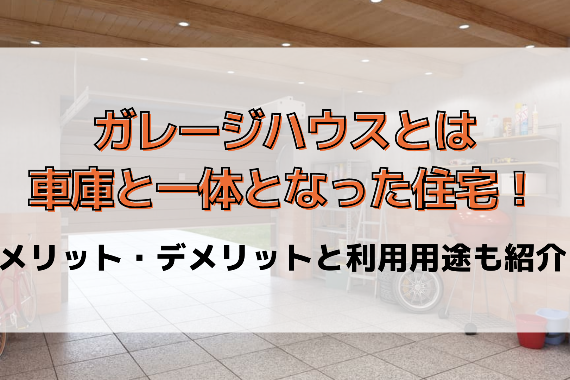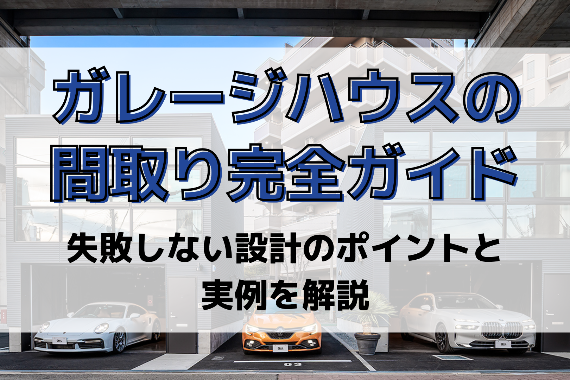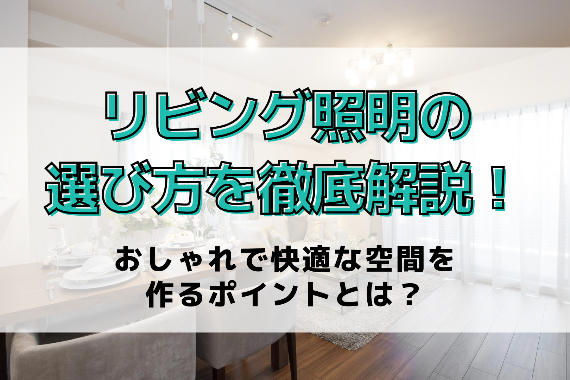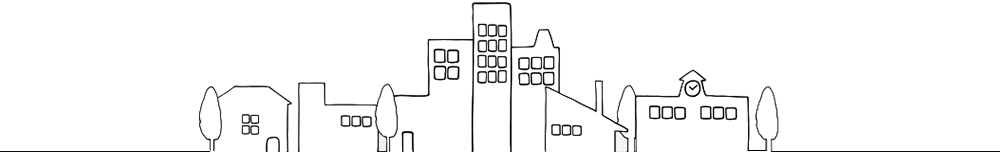布団のダニ対策を5つ紹介! 繁殖する要因や除去する方法も解説

布団はダニの餌となる人のフケやアカなどが溜まりやすく、ダニが繁殖しやすい環境です。1gのフケやアカがあれば約300匹生息できると言われており、対策をしていないと数千、数万のダニがいる状態となります。
ダニは人の肌を刺し、かゆみや炎症・アレルギー症状を発症させるなどの健康被害を引き起こします。そのため、布団にダニが繁殖しないよう日常的に対策をすることが大切です。
そこでこの記事では、布団のダニ対策について解説します。駆除や繁殖させない方法を具体的に紹介するので、ぜひ参考にしてください。
布団のダニは特に梅雨時期に対策が必要

ダニは高温多湿の環境を好みます。布団のダニ対策は一年を通して行う必要がありますが、特に温度と湿度が高い梅雨時期には駆除や繁殖予防を徹底することが重要です。
布団の中は、体温や寝汗などによって温度・湿度が高い状態になります。布団はダニの餌になるフケやアカが落ちやすいため、繁殖活動が活発な梅雨時期には何千倍にも増えてしまいます。梅雨から夏にかけてはダニが最も繁殖する時期であるため、特に徹底した対策を行いましょう。
布団のダニによる2つの健康被害

布団でダニが繁殖すると「かゆみや炎症」「アレルギー症状」などの健康被害が発生します。こちらでは、それぞれの具体的な症状や原因について解説します。
かゆみや炎症
かゆみや炎症は、ダニによる健康被害の代表的な症状です。かゆみや炎症の原因は、人を刺す「ツメダニ」です。ツメダニは吸血はしませんが、人の体液を吸うことでかゆみや炎症を引き起こします。かゆみや炎症は刺された直後には現れませんが、翌日以降に患部が赤く腫れて、1週間程度症状が続きます。患部を掻きむしると色素沈着を起こすなどの肌トラブルにもつながるため、ステロイド剤を使用するなどの処置を行いましょう。
ツメダニは、布団の中に生息する「ヒョウヒダニ(チリダニ)」を餌にして繁殖します。ヒョウヒダニ自体は人を刺すことがありませんが、ツメダニを繁殖させないためにも駆除しておくのがおすすめです。
アレルギー症状
ダニが繁殖すると、布団の中に死骸やフンが蓄積されます。死骸やフンは「アレルゲン」と呼ばれ、アレルギー症状の原因になる物質です。ダニによる代表的なアレルギー症状としては「アレルギー性鼻炎」「アトピー性皮膚炎」などが挙げられます。アレルギー症状は簡単には回復しない場合が多いため、予防を徹底することが大切です。特に免疫力の弱い小さな子どもや高齢者にとって深刻な問題につながるため、ダニを繁殖させないよう対策しましょう。
布団にダニが繁殖しやすい3つの要因

布団は、家の中でも特にダニが繁殖しやすい環境と言われています。ここでは、布団でダニが発生する原因について理解しておきましょう。
餌が豊富
布団には、毎日使っているうちにフケやアカが付着します。フケやアカを餌として生息するため、どうしても布団にはダニが増えてしまいます。そのためダニの繁殖を防ぐには、布団を常に清潔な状態に保つことが必要です。隠れやすい
ダニは明るい場所よりも暗い場所を好んで生息します。特に産卵時には、暗く狭い場所にもぐりこむ特徴があります。布団の中は繊維が密集しており外部の光が届かないため、ダニが隠れるのに最適な場所です。ダニの大きさは1mm以下と小さいため、布団の細かい繊維の間やファスナーなど様々な場所から布団の中にもぐりこむことが可能です。布団の表面は清潔に見えていたとしても、内部でダニが繁殖していることは少なくありません。
生息しやすい温度と湿度
布団は、家の中で最もダニが好む25度前後の温度と70%程度の湿度がある場所です。布団は寝汗と人の体温によって一定の湿度と温度が保たれています。また冬場であっても室内が暖房によって暖められることが多いので、一年を通して布団はダニが生息しやすい環境になっています。布団にダニを繁殖させない5つの対策

ダニの繁殖を防ぐには、日常的に布団を清潔に保ち、乾燥させることが大切です。こちらでは、布団にダニを繁殖させないための5つの対策を紹介します。
布団を敷きっぱなしにしない
布団は敷きっぱなしにせずに、定期的に日に当てて干すことが大切です。布団は敷いたままにしておくと餌となるほこりが溜まりやすくなる上、湿気がこもりダニが繁殖しやすい環境になります。特に梅雨時期には、毎日布団干し台にかけるようにしましょう。またベッドを使用している場合は、マットレスも立てかけるなどして通気を良くしておきましょう。
シーツや枕カバーをこまめに洗濯する
シーツや枕カバーは、こまめに交換して清潔に保つことが大切です。シーツや枕カバーは人の肌と直接接触するため、ダニの餌となるフケやアカが溜まりやすい場所です。週に1~2回は洗濯して、清潔なものに取り換えましょう。繊維の細かいシーツを使う
繊維の細かいシーツを使用することも、効果的な対策の1つです。ダニの大きさは1mm以下であるため、繊維の隙間から布団の中にもぐりこみます。しかしマイクロファイバー製など繊維の細かいシーツであれば、ダニは布団の中に入り込めません。またダニの侵入を防ぐために、縫い目の穴をテープで塞ぐなどの工夫が施されたシーツも市販されています。防ダニ加工の布団を使う
防ダニ加工が施された布団を使用することは、ダニ対策として有効です。防ダニ加工の布団には主に「防水加工」「薬品加工」された製品があります。防水加工の製品は汗を浸透させないため、布団の湿気を防ぐ効果が特徴です。薬品加工された布団は、忌避効果のある薬剤を使用することで、ダニを寄せ付けない性能を持っています。
ただし薬品加工された製品は、人によってはアレルギー反応を示す場合があります。免疫力の弱い子どもやお年寄りは薬剤加工の製品は避け、防水加工の布団や繊維の細かいシーツを使うと良いでしょう。
普段使っていない布団も定期的に干す
押し入れなどに保管している普段は使っていない布団も、定期的に干すことが大切です。押し入れは湿気がこもりやすく、布団にダニが繁殖している可能性があります。また保管する際にはスノコを敷くなどして、空気の流れを良くして布団の湿気を逃がす工夫をしましょう。布団にダニがいるか確認する方法

ヒョウヒダニの大きさは0.2〜0.4mm程度ですが、まとまった数の死骸がある場合は目視でも確認できます。布団に白い粉状のものが見える場合は、ダニの死骸である可能性があります。
また市販のダニ検査キットを使用することも、ダニの発見に効果的です。ダニ検査キットは誘引剤でダニをおびき寄せ、専用のルーペや顕微鏡で確認する仕組みです。また掃除機で吸い取ったゴミに薬剤を垂らして、ダニがいるか判定できるキットなどもあります。
ダニ検査キットはホームセンターやインターネットで購入可能です。キットの種類によって値段は大きく異なり、3,000〜10,000円程度で販売されています。
布団のダニを駆除する4つの方法

ダニは布団の中に生息しているため、表面を掃除機で吸い取っても駆除できません。こちらでは、ダニの駆除に効果的な4つの方法を紹介します。
掃除機でダニの餌を除去する
まず、ダニの餌となる髪の毛やフケやアカを掃除機で取り除きましょう。布団にダニの餌が残っていては、駆除してもまた繁殖してしまいます。ただしダニ自体は、かぎ爪と吸盤で布団にしがみついているため、掃除機では除去できません。ダニの餌を取り除く際は、布団たたきを使わず掃除機で吸い込むのがポイントです。布団を叩くとダニの死骸やフンが細かく砕けてしまい、内部に入り込んでしまうためです。
高温で死滅させる
ダニは「50度以上の熱で20〜30分」または「60度の熱」で死滅するため、天日干しまたは布団乾燥機で熱することで駆除できます。天日干しは真夏であっても布団が60度に達しないため、黒い不織布を布団にかけるなどの方法で日光を吸収させましょう。布団の中に入り込んだダニを駆除するためには、両面をしっかり日光に当てることがポイントです。
布団乾燥機を使う場合には温度を50度以上に設定し、90分から120分間使用します。一度に全てのダニを退治するのは難しいため、布団の表裏を2〜4回繰り返して乾燥することがおすすめです。
誘引シートで捕獲する
ダニの駆除には、市販されている誘引シートを使用することもおすすめです。誘引シートとは、薬品でダニをおびき寄せて粘着シートなどで捕まえる製品です。誘引シートは使用が簡単で、定期的に交換するだけで効果が持続します。誘引シートの持続効果は製品によりますが、一般的には1ヶ月に1度の交換が推奨されています。誘引シートは布団だけでなくカーペットやソファなど、他のダニが発生しやすい場所での使用も可能です。
布団を丸洗いする
布団の丸洗いはダニの餌となるフケやアカを完全に洗い流せる上に、高温の乾燥機で乾燥させることでダニを死滅できます。布団の丸洗いは、クリーニングサービスの利用がおすすめです。クリーニングサービスでは、専門の設備で布団を高温洗浄し、徹底的にダニの除去ができます。家庭での洗濯では難しい布団の内部まで、しっかりと清潔にできるため除去効果が高いです。
布団のダニ対策は発生を抑えるための日常的な工夫が大切

ダニ対策の基本は、繁殖を抑えるための日常的な布団のメンテナンスです。「布団を敷きっぱなしにしない」「シーツや枕カバーをこまめに洗濯する」など、小さな習慣がダニの繁殖を防ぐポイントになります。
さらに「天日干し」、「布団乾燥機」や「誘引シート」などの専用のダニ駆除製品を活用すれば、ダニが広く繁殖する可能性は低くなります。また、布団は定期的に丸洗いするなど、徹底的な対策を行えばさらに安心です。このように日常的な工夫と定期的な対策を組み合わせて、ダニの発生や繁殖を防ぎましょう。